 Ruby
Ruby Ruby
 Ruby
Ruby 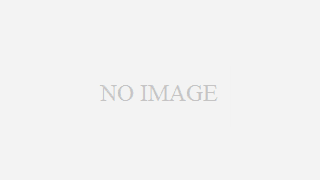 Rails
Rails destroy_allとdestroy_allと。
「destroy_allはdependent: :destroyを無視する」と記憶していたのですが、そうでもないよ、というはなし。ActiveRecord::Associations::CollectionProxyDeletes the ...
 Rails
Rails Kaigi on Rails 2025へ。
 Rails
Rails Kaigi on Rails 2024へ。
Kaigi on Rails 2024Kaigi on Railsのコアコンセプトは 「初学者から上級者までが楽しめるWeb系の技術カンファレンス」 です。 Kaigi on Railsは技術カンファレンスへの参加の敷居を下げることを意図し...
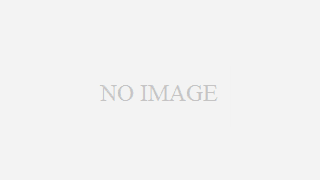 Ruby
Ruby freezeされた文字列リテラルのはなし。
# frozen_string_literal: true''.tap do |s| s << 'a' if a s << 'b' if b s << 'c' if cendみたいなことをしてcan't modify frozen Stri...
 Rails
Rails Kaigi on Rails 2023へ。
Kaigi on Rails 20232023.10.27 (Fri.) - 28 (Sat.) Hybrid event (online & offline) @浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス Keynote by @zzak ...
 Ruby
Ruby RubyKaigi 2023へ。
RubyKaigi 2023 - RubyKaigi 2023May 11th - 13th, 20232018年の仙台から5年ぶりの参加でした。忘れかけていたけれど、直に熱を感じられるってすばらしい。ありがとうございました!
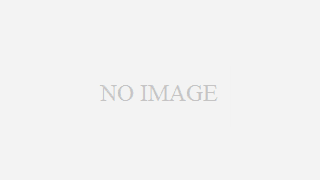 Ruby
Ruby Ruby 3.0.0 インストールしてました。
Ruby 3.0.0 リリースRuby 3.0系初のリリースである、Ruby 3.0.0 が公開されました。% rbenv install 3.0.0% rbenv global 3.0.0% ruby --versionruby 3.0....
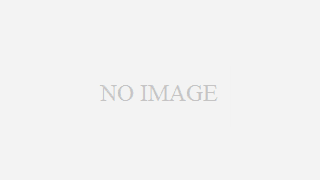 Ruby
Ruby Ruby 2.6.0がリリースされました。
Ruby 2.6.0 ReleasedRuby 2.6シリーズの最初の安定版である、Ruby 2.6.0がリリースされました。Ruby 2.6.0には、多くの新しい機能やパフォーマンスの改善が含まれています。その一部を以下に紹介します。いつ...
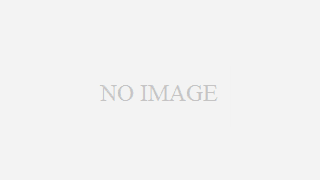 Rails
Rails Ruby on Rails 5速習実践ガイドを読みました。
普段はソロ活動が多く、他の方が書いたコードを仕事の中で読むことがほとんどないので、実践的な章はもちろん、入門的な章も知識の棚卸しとして読みました。自分にはまず、9章、10章が嬉しい内容でした。全体として具体的で「あぁ、トラブるな、そこ。」だ...